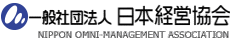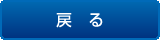セミナー詳細
| セミナー名 |
【行政管理講座】 個人住民税の課税実務入門【会場受講】 |
|---|---|
| 開催日時 | 令和7年11月13日(木)13:00~17:00 令和7年11月14日(金) 9:30~16:00 |
| 講師 | 寝屋川市 市民サービス部係長(税制・市民税担当) 三好 尚生 氏 |
| 会員参加料(税込) | 36,300円 |
| 一般参加料(税込) | 39,600円 |
| ねらい | 【本ページは、本会会場での受講の方のお申込み専用です】
オンライン中継視聴をご希望の方は、コチラからお申込みください。 市町村税の基幹税目である住民税は、その賦課(課税)徴収が地方自治体の財源の確保に多大な影響を与えるだけでなく、社会保障制度における給付や保険料等の負担に係る基準としての役割も担っています。このことから、住民税の課税事務の遂行にあたっては、地方税法等の法令の内容を正しく理解し適正に運用するとともに、住民に対しては、その課税根拠についての説明責任を果たすことが求められます。 本講座では、個人住民税の課税事務を担う初任者を主な対象に、個人住民税の制度概要から徴収方法、課税事務の年間スケジュール等まで、当該税目に係る課税事務の全体像を解説し、実務に求められる基礎知識を習得していただきます。 |
| プログラム内容 | 1.個人住民税とは (1) 個人住民税の種類 (2) 市町村民税の納税義務者と課す個人住民税 (3) 道府県民税の納税義務者と課す個人住民税 (4) 課税客体と課税標準 (5) 道府県民税、森林環境税の徴収について (6) 賦課期日 (7) 利子割、配当割、株式等譲渡所得割の納入 2.個人住民税の納税義務者と住所の認定 (1) 住所を有する個人とは (2) 住所の個数 (3) 住基外課税が行われた場合 (4) 事務所、事業所又は家屋敷を有する個人とは 3.非課税となる者 (1) 均等割及び所得割が非課税となる者 (2) 均等割が非課税となる者 (3) 所得割が非課税となる者 (4) 所得割の調整措置 4.均等割 (1) 標準税率 (2) 均等割の軽減 5.所得割の課税標準 (1) 課税標準(前年所得課税主義) (2) 課税標準(所得金額)の算定の原則 6.所得割の算出の流れ (1) 総所得金額等 (2) 所得控除 (3) 課税所得金額 (4) 所得割額 7.各種所得の金額の計算 (1) 所得税における所得区分 (2) 各種所得の計算方法等 8.青色事業専従者給与及び事業専従者控除 (1) 青色申告制度 (2) 青色申告の特典 (3) 青色事業専従者給与 (4) 事業専従者控除 9.各種所得の合計の仕方Ⅰ【損益通算】 (1) 損益通算とは (2) 損益通算が認められる損失 (3) 損益通算が認められない損失 (4) 損益通算の順序 10.所得合計から差し引かれる金額【所得控除】 (1) 所得控除とは (2) 所得控除の種類 (3) 所得控除の順序 11.所得割の税率 (1) 課税総所得金額等の計算 (2) 税率及び所得割額の計算 12.各種所得の合計の仕方Ⅱ【損失の繰越控除】 (1) 純損失の繰越控除 (2) 雑損失の繰越控除 (3) 繰越控除の順序 (4) 居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (5) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 13.株式等に係る譲渡所得に係る課税の特例 (1) 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 (2) 一般株式等、上場株式等に係る譲渡所得等 (3) 特定株式等譲渡所得の課税の特例 14.土地建物等の譲渡所得の課税の特例 (1) 土地建物等の譲渡所得に係る課税の特例 (2) 長期譲渡所得に係る所得割額の計算 (3) 短期譲渡所得に係る所得割額の計算 15.先物取引に係る雑所得に係る課税の特例 (1) 概要 (2) 所得金額の計算 (3) 税率 (4) 損益通算及び繰越控除 16.退職所得に係る課税の特例 (1) 退職所得に対する所得割の分離課税 (2) 納税義務者、課税団体等 (3) 分離課税に係る所得割の課税標準、税率等 17.所得割額から差し引かれる金額【税額控除】 (1) 調整控除 (2) 配当控除 (3) 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) (4) 寄附金税額控除 (5) 外国税額控除 (6) 配当割額、株式等譲渡所得割額の控除 (7) 定額による特別税額控除(定額減税) 18.個人住民税に係る申告等 (1) 住民税申告書 (2) 給与支払報告書 (3) 公的年金等支払報告書 19.徴収の方法 (1) 普通徴収 (2) 給与所得に係る特別徴収 (3) 公的年金等に係る特別徴収 20.個人住民税の賦課に係る業務スケジュール (1) 1月から12月までの各月における業務内容 21.地方税法総則分野における解説(参考) (1) 納税義務の成立と納税義務の確定 (2) 個人住民税の賦課決定に係る期間制限 (3) 課税標準等に係る端数計算 (4) 納税の告知(書類の送達) (5) 納税義務の承継 |
| 講師プロフィール | 寝屋川市 市民サービス部係長(税制・市民税担当) 三好 尚生 氏 平成17年 寝屋川市企画財政部税務室に勤務。個人住民税、法人住民税の賦課事務を担当。 平成29年 総務省自治税務局市町村税課において総務省自治実務研修を受講。 現在 寝屋川市市民サービス部(税制・市民税担当)にて市民税の賦課事務を担当。 |
| 対象 | 地方自治体の住民税の課税事務に従事する職員の方々 |
| 備考 | FAXでのお申込みはこちら |
| 持参物 | 当日は①地方税法(法律編)と②電卓をご持参ください。 ただし、スマートフォン、タブレット等の電子機器のご利用を以て代えていただいても結構です。 |
| 会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1-8-4大阪科学技術センタービル |
| 会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
| 会場電話番号 | 06-6443-6962 |
| 会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
| 問合せ先 | 企画研修G |
| 担当者 | 佐々木 |
| ksosaka@noma.or.jp | |
| パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |